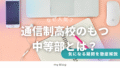不登校から始まった、長い模索の日々
不登校になってから、今年で3年。
最初の頃は、ただ家で兄弟で過ごす時間が増え、勉強や友達との関わりがほとんどなくなっていきました。
親としては「このままで大丈夫なのか」「将来どうなるのか」という不安が常につきまとっていました。
一番つらかったのは、子どもの笑顔が減ってしまったこと。
学校へ行けないことを責める気持ちはありませんでしたが、「楽しそうな姿を見たい」という願いだけは消えませんでした。
さらにようやく引っ越しをして見つけたフリースペースは、楽しそうに通うものの、雨だと行かない、気分が乗らないと行かないの繰り返しで、ついに1年経ったころぱたりと通わなくなりました。
他になにかいい方法はないかと模索の日々。

出会いは「ゲーム好き」がきっかけ
転機になったのは、eスポーツに特化したフリースクールとの出会いです。
ゲームが好きな我が子にとって、「ゲームが学びの中心にある場所」というのは、それまで想像もしなかった選択肢でした。
初めて見学に行った日、教室には大きなモニターやゲーミングPCが並び、生徒たちが真剣な表情で試合をしていました。
ただ遊んでいるのではなく、戦略を話し合い、ルールを守り、時には励まし合っていました。
その雰囲気を見て、正直に言えば私自身の「ゲーム=ただの遊び」という考えが少し揺らぎました。
さらに我が子たちの食いつきの良さ、初日から意気投合したお友達、先生、見学後に通いたい!
その食いつきにびっくりしたのを覚えています。
ゲームが「学び」に変わる瞬間
eスポーツには、さまざまなスキルが必要です。
・戦略的思考:どう動けば勝てるかを仲間と一緒に考える
・瞬時の判断力:試合中の状況に応じた行動の切り替え
・チームワーク:お互いの役割を理解し、助け合う
・コミュニケーション能力:チャットやボイスでの意思疎通
・感情のコントロール:負けても冷静に振り返り、次に活かす姿勢
こうした学びは、教科書や黒板の前だけでは身につきにくいものです。
ゲームを通じて自然と身につく姿を、私は何度も目にしました。
苦手な文字やキーボード操作も苦戦したものの、早かったです。

仲間とつながることで変わった笑顔
何よりも大きかったのは、「同じ趣味を持つ仲間」と出会えたことです。
学校では人と関わることを避けがちだった我が子が、ここでは自分から話しかけ、笑顔で過ごすようになりました。
試合前には真剣な顔で作戦を練り、試合後には勝っても負けても仲間と感想を言い合う。
その様子を見たとき、「この子はちゃんと人と関われるんだ」と心の底から安心しました。

親としての変化
私自身も変わりました。
以前は「ゲームばかりしていて大丈夫なの?」という不安が先に立っていましたが、今は「この経験がきっと将来につながる」と思えるようになりました。
家庭でも、ゲームの内容や戦略について話す時間が増え、自然と会話が多くなりました。
また、フリースクールの先生と定期的に情報交換することで、子どもの発達特性について理解が深まり、対応の幅も広がりました。
居場所は人それぞれ
eスポーツは、我が家の子どもたちにとって、自分らしくいられる大切な居場所になりました。
もちろん、すべての子にゲームが合うわけではありません。
でも「安心して自分を出せる場所」は、きっと誰にでもどこかにあります。
もし今、「うちの子はどこにも合わない」と感じている方がいたら、一度視野を広げてみてください。
その子が輝ける場所は、意外なところに隠れているかもしれません。

まとめ
eスポーツは単なる遊びではなく、学びの場にもなり得る 仲間とのつながりが、自己肯定感やコミュニケーション能力を育てる 親自身の価値観を柔軟にすると、子どもの可能性は広がる
ゲームでつながった仲間と過ごす時間は、我が子にとってかけがえのない財産です。
そしてそれは、親である私にも「新しい居場所の形」を教えてくれました。